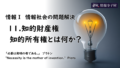こんにちは、なおや君。さて、前回は「知的財産権」のうち、「産業財産権」について学んだね。今回はもう一つの重要な権利である、「著作権」について勉強しよう。
黒板

授業
著作権の目的


いきなり法律の難解な文章を出されても、まったく頭に入ってきません。もう少しわかりやすくお願いします。

文化の発展ですね。頑張って勉強します。
著作者人格権

著作者の人格ってどういうこと?

良い質問だね、なおや君。著作者の人格とは、著作者の創作活動や表現に関するアイデンティティや、その作品に対する精神的なつながりを指すよ。つまり、著作者が自分の作品に込めた思いや、表現したいことが守られることが大事なんだ。

ふーん。どんな時にその権利が侵されるの?

著作者人格権が侵される状況は、例えば作品が無断で改変されたり、著作者名が不当に表示・削除されたり、作品の公表が著作者の意思に反して拒否されたりする場合だよ。

なるほど、著作者人格権があるおかげで、著作者の大切な名誉が守られるんだね。では、著作者財産権についても説明して。
著作権(財産権)

なんとなくわかったような、わからないような。それぞれ説明して。
複製権

複製権は著作物をコピーする権利だよ。たとえば、音楽をダウンロードするのもこれにあたる。

複製権って、家で勉強のために教科書をコピーするのもダメなの?

勉強のための教科書のコピーは、私的使用目的であれば問題ないよ。これは、著作権の例外事項として定められていることなんだ。ただし、他人に譲渡したり、営利目的で利用することは禁止されているから注意してね。
上映権

上映権は、映画を映画館で上映してよいという権利かな?

そうだね。上映権は映画館に限らず、映像作品を公に上映する権利だから、YouTubeやTikTokなどの動画配信も上映権が関係してくるよ。

えっ。TikTokに動画をアップしても違法になるの?

自分で撮影したオリジナルの動画や、著作権者から許可を得た場合は問題ないけど、著作権者の許可なく他人の動画をアップロードすると、著作権法に違反することがあるから注意してね。

映画館でいつも流れる、NO MORE映画泥棒も、この関係?

そうだね。でも、あれは少し複雑で、映画盗撮防止法という法律が絡んでいるんだ。

複製権と、上映権で速攻アウトじゃないの?

実は、複製権にも例外規定があって、「私的利用のための複製」はOKなんだ。

だったら、映画を撮影して個人で楽しむのはOKということ?

そういう解釈になるよね。でも、個人で楽しむと言って録画して、それをYoutubeにアップするかもしれないよね。

うん、そうなると思う。

だから映画館等における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱って、例外規定を適用しないという法律を作ったんだ。

なるほど。例外の例外というわけですね

その通りだね

No MORE映画泥棒にはそんな深い意味があるとは知らなかったな。

譲渡権

譲渡権は著作物を売ったり、著作権を他人に譲る権利だよ。

具体的にどんな時に発生するの?

譲渡権は、著作物の所有権を他人に移すときに発生するよ。例えば、絵画や彫刻を売買する場合や、ある会社が自社が持っている著作権を別の会社に売る場合などがこれにあたるね。
二次的著作物の創作・利用権とは

二次的なんとかいったけど、それは何?

二次的著作物の創作・利用権のことかな

ずいぶん長い名前だけど、どういう権利?

二次的著作物の創作・利用権は、既存の著作物を元に新しいものを作る権利だよ。例えば、小説を映画化するのがこれにあたるね。

ちなみに、YouTubeとかで映像を加工してアップロードするのは合法なの?

それは状況によるんだ。例えば、著作物を引用する場合は、著作権法の「引用」の規定に基づいて、適切に引用すれば合法だよ。ただし、引用の範囲を超えて著作物を利用したり、二次的著作物を作る場合は、著作権者の許可が必要になるね。

なるほど、引用の範囲内で使う分には大丈夫なんだね。でも、どこまでが引用の範囲なの?

引用の範囲は、具体的な基準がないから難しいんだ。ただ、一般的には、引用の目的に応じて必要最小限の範囲内で利用することが求められるよ。

じゃあ、例えば、映画の一部を引用してレビュー動画を作るのは大丈夫なの?

そうだね。映画の一部を引用してレビュー動画を作る場合、必要最小限の範囲で引用すれば合法だと言えるよ。

でも、もし引用の範囲を超えて使ってしまったらどうなるの?

引用の範囲を超えて利用した場合、著作権侵害になる可能性があるね。その場合、著作権者から損害賠償請求を受けることがあるよ。

なるほど。よくわかったよ。でも、著作権を守ることと、それを活用することのバランスは難しいなぁ。

確かに、権利者の利益を守りつつ、他人がその知的財産を活用できる範囲を適切に設定するのは難しいことがあるね。

じゃあ、どうすればいいの?
クリエイティブ・コモンズ

まず、自分が利用しようとしている知的財産がどのような権利で保護されているかを確認しよう。その上で、引用やパロディなど、法律で認められている範囲内で利用することが大切だね。また、クリエイティブ・コモンズのようなライセンスを活用することで、権利者が許諾した範囲で自由に利用することができるよ。

クリエイティブ・コモンズって何?

クリエイティブ・コモンズは、著作権者が自分の作品をある程度自由に利用してもらいたい場合に、利用条件を設定できるライセンス体系だよ。例えば、非営利目的での利用や、改変や再配布を許可するなど、様々な条件が選べるんだ。
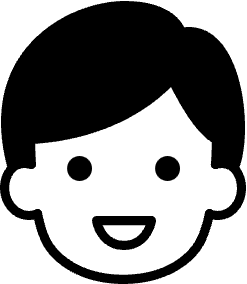
なるほど、クリエイティブ・コモンズを使えば、権利者の意向に沿った利用ができるんだね。

そうだね。権利者の意向に沿った形で情報が共有され、新たな創造が生まれる。だからこそ、知的財産権の理解と活用は、情報社会で生きる我々にとって重要なんだ。

まとめ
- 著作者人格権
著作者が保有する人格的利益を守るための権利であり、著作者の名誉・信用を守るための権利や、著作物の改変や不当な利用を防ぐための権利が含まれる。 - 著作権(財産権)
著作者が保有する財産的利益を守るための権利であり、著作物を複製、上映、譲渡、二次的著作物の創作や利用をする権利が含まれる。 - 二次的著作物の許可
著作物を元に新たに作品を創作する場合には、元の著作権者から許可を得る必要がある。 - 譲渡権
著作物の所有権を移す権利であり、著作者は自身の作品の著作権を譲渡することができる。 - クリエイティブ・コモンズ
著作権者が自分の作品をある程度自由に利用してもらいたい場合に、利用条件を設定できるライセンス体系。
名言
“Code is law” Lawrence Lessig
ローレンス・レッシグは、ハーバード大学法科大学院の教授であり、インターネット法と著作権法の権威として広く認識されています。彼はクリエイティブ・コモンズの設立者であり、著作権とデジタル技術の交差点についての深い洞察を提供しています。
レッシグの言葉「コードは法律である」は、インターネットやデジタル世界での行動がその背後にあるプログラム(つまり「コード」)によって大きく制約され、それが実質的な「法律」の役割を果たすという概念を示しています。
例えば、スマートフォンで音楽を聴くとき、そのアプリのプログラム(コード)がどの曲を聴けるか、どの曲をダウンロードできるかを決めていますよね。これと同じように、インターネット上で何ができて何ができないかは、ウェブサイトやアプリのプログラム(コード)によって決まります。
この考え方は、クリエイティブ・コモンズとも密接に関連しています。クリエイティブ・コモンズのライセンスは、著作権者が他の人にどのように自分の作品を使ってもらえるかを明確にするためのものです。例えば、他の人が自分の作品を自由に改変したり、商用利用したりすることを許可するかどうかを決めることができます。これにより、作品の使用がより柔軟になり、クリエイティビティが広がる可能性があります。
レッシグのこの言葉は、インターネット上での行動がどのように制約されるのか、そしてそれがどのように私たちの行動に影響を与えるのかを理解するのに役立ちます。これは著作権や、他の人が作ったものをどのように利用できるのかといった問題を考える上でも重要な視点となります。
問題
「クイズをスタート」のボタンをクリックすると、5問出題します。さあチャレンジ!
編集者よりひとこと
ローレンス・レッシグの”Code is law”は、Web3.0の文脈では頻繁に登場する、重要な概念です。インターネットが現在の2.0から3.0に進化する事で、現在のインターネットの問題の多くを解決してくれる可能性があります。しかし、今後どのように進化するのか未知数のところが多いので「情報Ⅰ」の授業では取り扱われていないようです。しかし、レッシグがそのビジョンを形成したクリエイティブ・コモンズについては、情報Ⅰの教科書に書かれており、これを見てちょっとうれしくなりました。
普段Youtube等を見ていても、その動画が何のライセンスに基づいて公開されているのか意識することは少ないと思いますが、検索窓に、検索文字につづき「creativecommons」と入れると、該当する動画が表示されます。動画を活用したいと考えている人はやってみてください。
さて次回は、いよいよ「情報社会の問題」の最後の授業となる、「知的財産の保護期間」です。お楽しみに。
<RANKING>![]()
高校教育ランキング